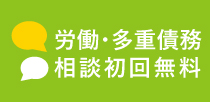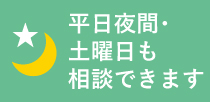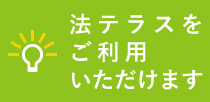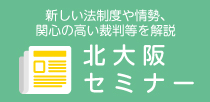アベノマスク契約締結経過文書の情報公開訴訟で国の不開示決定を大部分取り消し、国家賠償も命じた勝利判決が確定
1 「アベノマスク」と2つの情報公開訴訟
「アベノマスク」。新型コロナウイルスが一気に拡大し始めた2020年4月1日、政府対策本部において安倍首相(当時)が突如、全世帯に布マスクを2枚ずつ確保し配布すると発表しました。巷では「エイプリルフールの冗談では」との声が相次ぎ、その不格好な見た目も相まって「アベノマスク」と揶揄されました。これは、購入費だけで約440億円、配布や検品、コールセンター等の経費で約100億円、合計540億円超もの巨額の税金が、極めて短期間に支出された政府事業です。
アベノマスク事業は、虫の混入やカビを原因とする回収騒ぎや、市場に不織布マスクが出回り始めたにもかかわらず一向に届かないといった混乱を招きました。また、政府の購入単価は国民に明らかにされず、調達業者には「ユースビオ」のような設立後わずか3年の実態不明な会社まで含まれるという疑惑も生じました。
こうした疑惑報道の渦中であった同年4月下旬、上脇博之神戸学院大学教授(後に自民党派閥の裏金問題で注目されることとなる)が、厚生労働省と文部科学省に対し、①「調達業者とのやり取りを記録した文書」、②「調達業者とやり取りした文書そのもの」の情報公開を請求しました。すると、①は全て不存在、②は見積書、契約書、納品書等を除いて不存在という決定(不開示決定)がなされました。500億円以上の税金が支出された政府事業において、随意契約の業者選定や発注経過に関する文書が一切残っていないという、信じがたい結果でした。しかも、開示された契約書等では「単価」が事業者の利益等を理由に不開示(マスキング)とされていました。
この不可解な不開示決定に対し、上脇教授は大阪地裁に2つの訴訟を提起しました。一つは契約書等の単価不開示の取消を求める訴訟(2020年9月提訴)、もう一つが、今回判決が出された、契約経過文書を不存在とした点の取消と国家賠償を求める訴訟です(2021年2月提訴)。
先行した単価訴訟では、2023年2月28日、大阪地裁(徳地淳裁判長)が不開示決定を取り消し、開示を命じる判決を言い渡しました。国は控訴を断念し、単価に関する文書が開示されました。その結果、業者間で倍以上の単価差があったことが判明しましたが、その経緯は依然として不明なままでした。
2 契約締結経過文書不存在訴訟での国の迷走
並行して審理されていた契約経過文書訴訟で、国は迷走を続けました。
当初、情報公開請求時には「文書は作成していないので不存在」と説明していましたが、訴訟提起後の答弁では「実は業者とのメールはあった(作成・取得していた)が、1年未満保存文書としてその都度廃棄していた」と主張を変えました。その後、原告側は「業者側にはメールが残っているはずだ」として、裁判所に調達業者17社への送受信メール提出を求める文書送付嘱託を申し立て、これが採用されます。すると、数社から大量のメールが裁判所に送付されました。
慌てた国は「文書を再探索するため少し時間が欲しい」と述べ、期日を数回にわたり空転させた後、「職員のパソコンに100通以上のメールが見つかった」「紙文書もいくつか見つかった」と明らかにしました。裁判長が国に対し「その点については不開示決定を取り消し、開示決定をやり直すのか」と質したところ、国は「検討する」と述べたあげく、「情報公開請求の対象文書を『組織としての意思決定が記載されるもの』などに限定して解釈していた」という新たな主張(対象文書の「限定解釈」)を展開。再探索で発見されたメール等は、この限定解釈した対象文書に該当しないため、不開示決定は取り消さない、と強弁したのです。その後、送受信したメールが1年間バックアップファイルに保存されていたという新事実も明らかになりました。
このように国は、徹頭徹尾「アベノマスク関連文書は何もない、あっても開示しない」という結論ありきで、新たな事実が発覚するたびに、その場しのぎで主張を変えるという、あからさまな態度を続けました。裁判終盤には、厚労省、文科省の管理職や職員、調達実務を担った経産省からの応援職員ら6人の証人尋問が実施されましたが、いずれも「当時の状況は多忙を極めた」「チーム内のやりとりは全て口頭だった」「メールボックスがいっぱいになるので2~3日に一度は捨てていた」「業者とのやりとりや面会の記録は一切作成していない」と口を揃えました。この明らかに不自然で不合理な証言には、裁判官からも「高額な売買なのに、口頭のやりとりで金額を間違えたらどうするのか」といった、素朴な疑問が呈されました。
3 大阪地裁判決の内容と国の控訴断念
2025年6月5日、大阪地裁判決(徳地淳裁判長)は、本件の情報公開請求に対し、国がそもそも情報公開の対象となる1年未満保存文書(内部の報告書やメール等)を一律に探索や開示の対象としていなかったと断じました。その上で、①マスク購入に関する業者との交渉経過の記録(報告書やメール等)、②業者との打合せ記録、③興和(株)への契約不適合責任免除特約の付与経緯、④興和(株)との大幅値下げの経緯、⑤マスク回収の経緯、⑥調達業者との送受信メール及び添付文書など、対象となったほとんどの文書について、「これらを一通も作成・取得せず、決定時に保存していなかったとは考えられない」として、各不開示決定を取り消しました。
さらに、国が「再探索」後に限定解釈の主張を始めた点については、「開示決定のやり直しを迫られたため、事後的にその解釈を考え出して主張するに至ったと考えざるをえない」と断じ、国が本訴訟で意図的に事実に反する主張(要するに虚偽の主張)を行ったことを厳しく指弾しました。そして、このような公文書管理法や情報公開法を無視した対応は国家賠償法上も違法であると認定し、国に原告への損害賠償(11万円)を命じました。民主主義の根幹たる公文書の作成・保管や情報公開について、裁判所がこれほど厳しく国の姿勢を批判し、「嘘」の主張を明確に認めて断罪したことは、極めて大きなインパクトがあります。
国は控訴期限までに控訴せず、同月20日に判決は確定しました。これにより、国はこれまで不存在としてきたアベノマスク事業の関連文書を探索し、開示することになります。原告は判決確定を受け、石破内閣総理大臣や厚労大臣・文科大臣に対し、①判決内容の完全な履行と関連文書の即時全面公開、②本件の経緯と訴訟における意図的な虚偽主張の徹底調査と責任の明確化、③公文書管理制度の抜本的改革と再発防止策の策定、④アベノマスク事業自体の調査・検証、という4項目の申入書を提出し、回答を求めています。一連の情報公開訴訟はこれで終結しますが、今後も監視と追及を強めていく所存です。
(当事務所から徳井弁護士と谷が弁護団に参加)