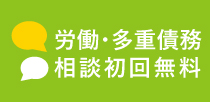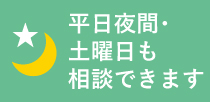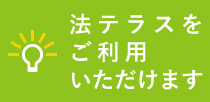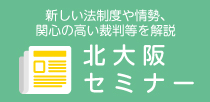【書評】谷真介著「定年・再雇用の法律実務」(旬報社) =これ一冊で理論と実践の全てがわかる本=
【書評】 谷真介著 「定年・再雇用の法律実務(最新テーマ別[実践]労働法実務<8>)」(旬報社 全13巻中の第8巻) =これ一冊で理論と実践の全てがわかる本=
✿ 徹底的に実用的
本書は、「最新テーマ別「実践」労働法実務」(旬報社)全13巻のシリーズの8巻目である。本シリーズのコンセプトは、「徹底的に実用的」ということにあり、各巻ごとに、全国各地で活躍している労働弁護団所属の中堅・若手の弁護士が執筆している。著者は、労働弁護団、民法協の幹事であり、中堅弁護士の代表格である。私と同じ北大阪総合事務所の所属でこれまで数多くの労働事件を一緒に担当した。また、シリーズの編者の一人は、第1巻の著者でもある城塚健之弁護士である。
✿ 至れり尽くせりの書
さて、少子高齢化が進行し、労働力不足と高年齢者の就業意欲の高まり、年金支給年齢の引き上げ等が相俟って、就業者の高年齢化が進み、高年齢者の雇用と労働条件、就労環境を守ることが大きな課題となっている。他方で、定年と継続雇用をめぐる法律問題については、労働法の基本書ではまとまった記述はなく、また、実務書も経営側の弁護士の側の書籍はいくつかあるが、労働者側の立場から書かれたまとまった書籍はなかった。
本書は、労働者側の観点から、定年・再雇用をめぐる全ての法律問題に関して、裁判例を網羅し、最先端の学説もフォローし、相談を受けた際の留意点、いかなる手段を選択するかの判断要素、更には申入書、労働審判申立書、訴状の案なども付されている。また、高年齢者の社会保険や高年齢雇用継続給付金等の制度の丁寧な解説もなされている。定年・再雇用の理論と実践の全てがこの一冊でわかる、まさに「至れり尽くせりの書」といってよい。
✿ 定年・再雇用をめぐる法律問題
ところで、「定年・再雇用」をめぐる法律問題は、大きくわけて、①60歳定年到達時の再雇用拒否、②再雇用後の雇止め、③再雇用後の労働条件をめぐる争いがある。
上記①の紛争類型については、2004年高年齢者雇用安定法(高年法)改正下では再雇用者の選別制度が導入され、恣意的に再雇用を拒否される紛争が続発した。著者である谷弁護士と私が担当した津田電気計器事件は、組合員であるがゆえに恣意的に低査定され、基準点に達しないとして再雇用を拒否された事案であった。使用者が再雇用契約の締結を拒否しているのに、いかなる法的構成で再雇用契約の成立を肯定できるのかが最大の理論的な問題であり、当時、先例となる裁判例はなかった。また、広範な裁量が認められる傾向にある使用者側の査定の誤りをどう主張立証するかという壁もあった。
前者は、西谷敏先生、根本到先生らの論文をもとに法的構成をし、地裁、高裁と勝訴した。そして、本書でもリーディングケースとして紹介されている最高裁判決(平成24.11.29)は、有期労働契約の雇止め法理を転用するという法的構成で再雇用契約の成立を認める初判断をした。後者の「査定の誤り」は、谷弁護士が尋問間際に原告の過去の表彰状を提出し、これが再雇用規程上プラス5点にカウントされ、結果的にぎりぎりで継続雇用の水準を超えると判断されることにつながった。これがなければ最高裁判決はなかったかもしれない。谷弁護士の果たした貢献は大きい。
その後、2012年高年法改正によって希望者全員の雇用が法的義務となり、選別制度も2025年3月末までに段階的に廃止されたが、「解雇事由」等ある場合、再雇用を拒否されるという紛争は残っている。本書では、津田電気最高裁判決の意義、内容とその射程、再雇用拒否訴訟における攻撃防御方法、最新の裁判例を丁寧の紹介し、複線的な制度、選択雇用制などの特殊な紛争類型についても解説を加えている。
✿ 労働弁護士魂
現在の実務上の主たる焦点は、上記③の紛争類型である再雇用後の労働条件をめぐる紛争に移っている。60歳になり再雇用された途端、同じ仕事をしているのに賃金が激減する、いわゆる「60歳の崖」として社会問題となっている。
本書でも解説されているとおり、法的な対応としては、高年法の趣旨・目的からのアプローチと旧労働契約法20条(パート有期法8条、9条)からのアプローチがある。先例として前者には、2つの高裁判決(九州総菜事件、トヨタ自動車事件)、後者には2つの著名な最高裁判決(長澤運輸事件、名古屋自動車学校事件)がある。これらは、労働法学会でも数多くの論文や評釈が出ているところであるが、実際の相談に際して、個々の事案ごとにどのように対応するかは決して容易ではない。
また、前者の2つの高裁判決は、高年法の趣旨、目的のとらえ方が異なっている。後者は、基本給・賞与の相違に関する名古屋自動車事件・差戻審(私も弁護団に加えてもらった)が係属中であるなど、裁判実務上も必ずしも確定しているとはいえない分野である。谷弁護士から本書の原稿作成の段階で、何回か意見を聞かれ、議論した論点でもある。
本書では、2つのアプローチについて、場合を分けて、問題点と取り得る手段について丁寧に解説されている。そのなかで意識し、貫かれているのは、城塚弁護士の本書のはしがきにある「現在の裁判所の判断を踏まえながらも『人間の尊厳』のためにあるべき法解釈はどのようなものであるかを考え、おかしいものはおかしいと主張し、変えていく努力をすべき」という労働弁護士魂である。本書を読むにあっては、マニュアルとしてだけでなく、そのような谷弁護士の心意気を感じてもらいたいと思う。
✿ 実務の到達点や課題を知る
最後に、労働事件は、類型は同じであっても、事実関係や証拠関係で争い方は変わる。「定年、再雇用」の相談についても、事案に向き合い、いかなる発想で、いかなる法的な手段で争うのか、自分で考えるのが基本であるが、現在の実務の到達点や課題を知ることも不可欠である。その際、是非、その際に本書を参考にされることをお勧めする。
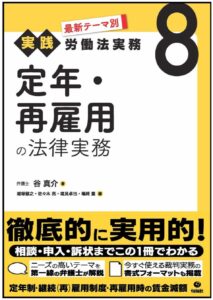
出典:旬報社ホームページ
最新テーマ別[実践]労働法実務シリーズについての旬報社の特設サイト
2025年8月27日出版 A5・400頁 定価4,400円(税込)